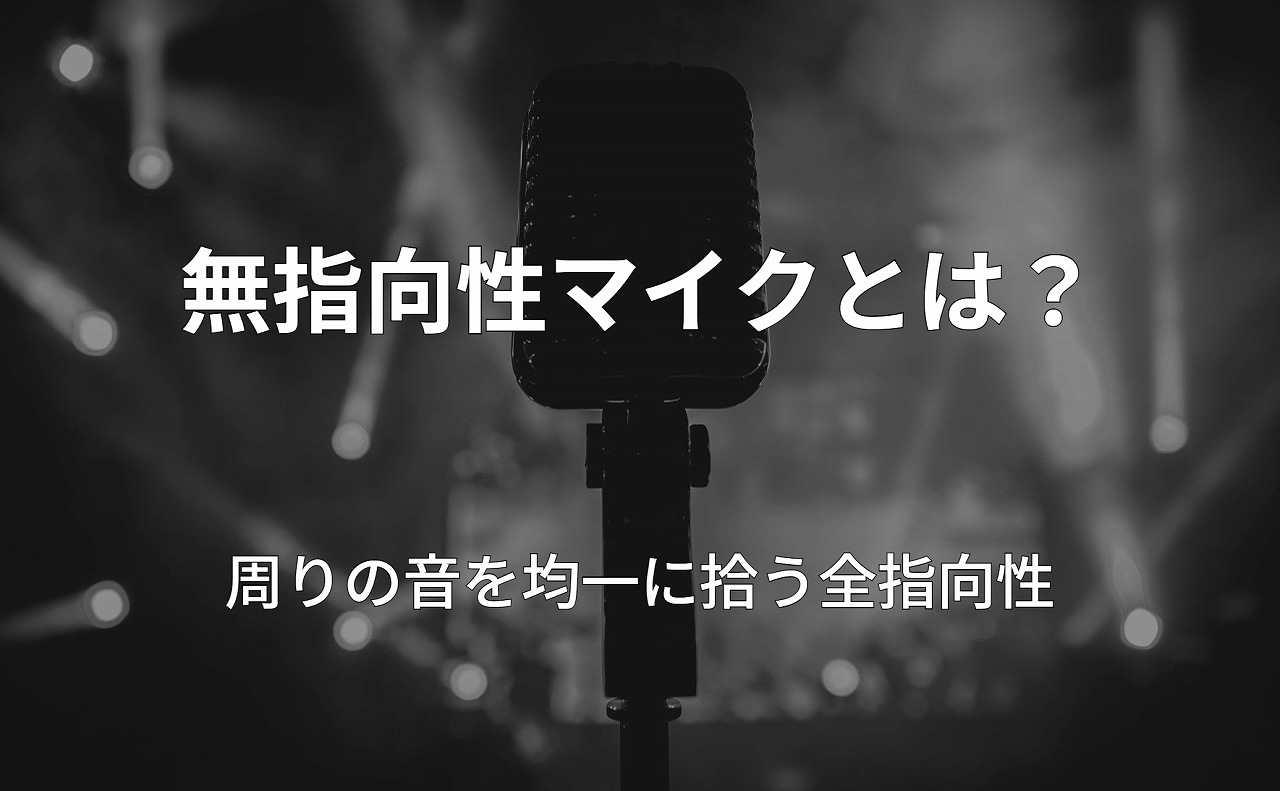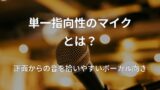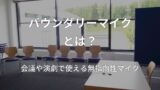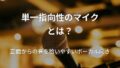マイクには、さまざまな種類のものがあり、用途に応じて使い分けることが基本となります。
その中でも、指向特性というもので分かれており、どの方向からの音を拾いたいのかでどの種類にするか決めていく必要があります。
上記のページに、それぞれの指向性についてまとめていますが、特に指向性を持たないものを無指向性と呼びます。
無指向性マイクの特徴は、マイクの周りの全ての音を均一に拾うことで、全指向性マイクとも呼ばれます。
このページでは、無指向性マイクについてどんなマイクなのか、またどの用途に向いているか、おすすめのマイクまでをまとめていきます。
無指向性(全指向性)マイクとは?
まずは、無指向性(全指向性)マイクがどのようなマイクなのかをまとめていきます。
マイクの指向性と無指向性の違い
冒頭でも解説した通り、マイクには指向性と呼ばれるマイクの特定の方向からの音を捉えやすい性能を持っています。
例えば、カラオケのマイクなどは単一指向性と呼ばれる指向特性を持っており、マイクの正面からの音を最も拾いやすく、反対にマイクの背面からの音は拾いにくい性能を持っています。
一方で、無指向性マイクは、この指向特性を持っていないマイクのことを言います。
具体的には、無指向性はマイクの正面からだけでなく背面、横面などマイクの周り360°全ての音を均一に拾ってきます。
そのため、全ての方向に対して指向性があるとも言えるので、無指向性マイクは全指向性マイクとも呼ばれます。
ノイズや騒音を拾いやすい
無指向性マイクは、部屋や周りのノイズ・騒音を拾ってしまうことが多いです。
具体的には、部屋のエアコンや換気扇、屋外での話し声など、マイクで拾いたい音以外も無指向性では拾ってしまうことがあります。
特に、近くに人がいたり、作業していたりすると、マイクの反対側にいても音が拾われやすいです。
そのため、ノイズが発生しやすく、音楽のレコーディングなどでは使われることがありません。
なお、レコーディングなどで良く使われるのは、特定の方向からの音に対して感度が高い単一指向性のマイクになります。
ハウリングが発生しやすい
ハウリングとは、キーンという不快な音が発生してしまう現象で、原因はマイクで拾った音をスピーカーで流した際に、そのスピーカーの音が再度マイクで拾われてしまい、特定の周波数帯だけが増幅してしまうことです。
無指向性マイクは、このハウリングが発生しやすいというデメリットを持っています。
なぜなら、無指向性マイクはどの方向からの音もしっかりと拾ってくるため、どの位置に設置してもスピーカーの音を拾ってきてしまうからです。
そうなると、先ほどの通りでハウリング現象が起きやすくなってしまいます。
そのため、講演会場やライブ、ステージなどで無指向性マイクが使われることはありません。
無指向性(全指向性)マイクに適した使い方・用途
無指向性マイクは、全ての方向からの音を拾ってくれるものの、ノイズやハウリングが発生しやすいことが分かりました。
それでは、無指向性マイクはどのような使い方が適しているのでしょうか?
会議
会社などの会議などでは、無指向性マイクは非常に効果的です。
なぜなら、会議では複数人が参加することが多く、参加者が様々な方向からしゃべることが想定されるからです。
具体的には、支店が複数ある際の会議などで、それぞれの支店の会議室の真ん中に無指向性マイクを設置しておくことで、全ての人の声を捉えることができます。
もし、指向性を持ったマイクにしてしまうと、参加者毎にマイクを準備する必要があり、金額も手間もかかってしまいます。
そのため、会議では無指向性マイクが合いやすいです。
PC用マイク
パソコン(PC)用のマイクとしても、無指向性マイクは使われることがあります。
なぜなら、指向性を持ったマイクだと、動いたり喋っている方向を変えてしまうと、聞き取りづらくなってしまうことがあるからです。
無指向性マイクを使うことで、作業をしながらでもしっかりと声を伝えることが出来ますし、設置する場所も気になりません。
ただし、自宅などだと他の部屋の騒音も拾ってしまうことがありますので、状況に合わせて無指向性マイクにするか、指向性マイクにするかを判断していきましょう。
ドラムの収音
ボーカルや楽器のレコーディングでは、あまり使われることが無い無指向性マイクですが、ドラムの収音に使われることがあります。
ドラムセットのそれぞれの楽器に対しては、単一指向性マイクなどで拾ってくることが多いですが、ドラムの生の響きや空気感を捉えるために、無指向性マイクは使われます。
具体的には、ドラムブースの天井の高い位置に無指向性マイクをセッティングすることで、前述の通りドラムの響きを捉えることができます。
また、その他の楽器でも響きや空気感を大事にする場合は、無指向性マイクが使われます。
おすすめの無指向性(全指向性)マイク
無指向性マイクがどんなマイクなのかが分かってきたところで、おすすめの無指向性マイクを紹介していきます。
TOMOCA / EM-700

無指向性のピンマイク型コンデンサーマイクで人気があるのが、TOMOCAのEM-700です。
楽器などに取り付けるホルダーも付いているので、楽器の音を無指向性で収音したい場合にもおすすめです。
マイク本体も100gと軽く、非常に手ごろに使うことができます。
また、価格帯も4,000円前後ながら感度も良く、コスパの良い無指向性マイクと言えます。
JTS / CX-500

楽器用のラベリアマイクとして、JTSのCX-500もおすすめマイクのひとつです。
バイオリンやギターなどの弦楽器に直接装着して使用することで、より高いクオリティの音を拾うことができます。
また、無指向性タイプを使うことで、楽器内の響きまで拾うことが出来るので、単一指向性とはまた異なる音を楽しむことができます。
こちらも6,000円前後とマイクの中では比較的安い分類に入りますが、音は非常に良く拾ってくれます。
サンワサプライ / MM-MCU06BK
サンワサプライから発売されているMM-MCU06BKは、パソコンを使った会議用に適しているUSB型のマイクです。
会議やSkype通話など、特に複数人の声を拾いたい場合に、このマイクを中心に置いておくことで、全ての人の声を拾ってこれます。
また、USB型のマイクなので、パソコンのUSB端子に繋いで簡単に使うことができます。
小型サイズでもあるので、出張先での会議などにも対応することができます。
まとめ
このページでは、無指向性マイクについてまとめていきましたが、いかがでしたでしょうか?
無指向性マイクの特徴は、
- マイクの周りの全ての音を捉える
- ノイズやハウリングが発生しやすい
となります。
特に、後者のノイズやハウリングの現象が起きやすいため、あまりマイクで選ばれることが無いですが、周りの環境が静かであれば、音の響きをより捉えることが出来るのも無指向性の強みです。
また、複数人の声もしっかりと拾うことが出来るので、無指向性マイクは1本持っていても良いと思います。
特に、バウンダリーマイクと呼ばれる無指向性マイクは、床や壁に設置して使用でき特定の業種では使われることが多いマイクです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!