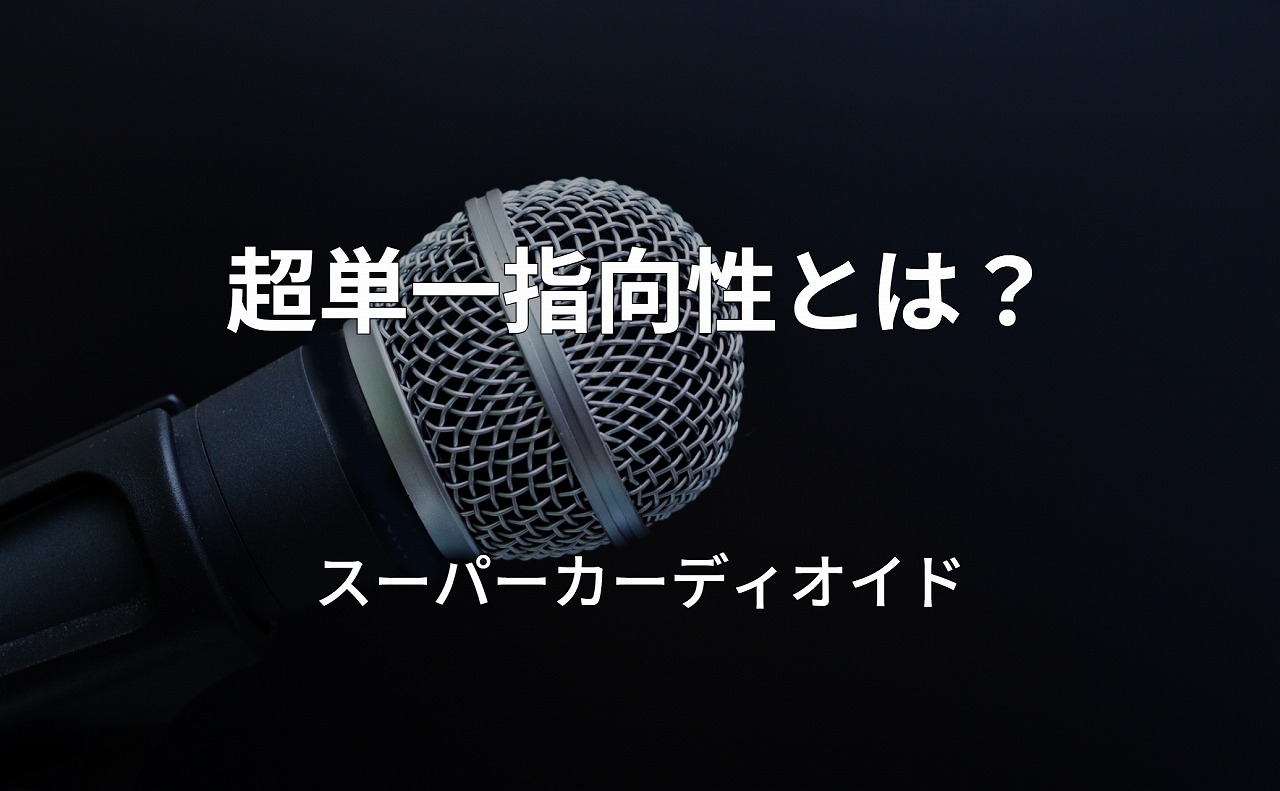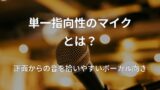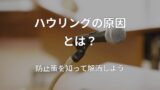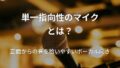マイクを選択する際のポイントとして、指向特性というものがあります。
指向特性は、マイクの特定の方向からの音を拾いやすく、それ以外の音を拾いにくくしている性質を表しているものです。
上記ページでもまとめていますが、指向特性には大きく3つに分かれており、マイクの正面からの音を拾いやすくしているのが単一指向性と呼ばれるマイクです。
この単一指向性の中でも、周りの音を拾いにくくして、より正面の音を引き立てるように設計されているのが、超単一指向性(スーパーカーディオイド)のマイクです。
このページでは、超単一指向性(スーパーカーディオイド)について、どんなマイクなのか、用途やおすすめのマイクをまとめていきます。
超単一指向性(スーパーカーディオイド)とはどんなマイク?
超単一指向性は、超指向性やスーパーカーディオイドとも呼ばれることがあります。
この超単一指向性マイクが、どんなマイクなのかをまずはまとめていきます。
単一指向性と超単一指向性の違い
冒頭でも解説しましたが、マイクの正面からの音を拾いやすい特性を単一指向性と呼びます。
超単一指向性も同じように、マイクの正面からの音を拾いやすいのですが、より狭角に拾うのが単一指向性とは大きく違います。
具体的には、単一指向性がマイクの正面から音を拾う範囲は131°となりますが、超単一指向性は115°となっており、より狭い範囲の音を拾う設計になっています。
単一指向性よりも指向性を狭角にすることで、より遠くの音を拾い集めることを可能にしたのが、この超単一指向性(スーパーカーディオイド)です。
超単一指向性マイクの分類
超単一指向性マイクには、構造的に2種類に分類されます。
干渉管を使用する干渉管型と、2つのマイクロフォンユニットを用いる二次音圧傾度型です。
干渉管型の場合は、専用のマイクロフォンユニットの先端に長めの筒を取り付けて、アコースティック的に指向性を狭角にしているものです。
一方の二次音圧傾度型の場合は、単一指向性マイクを2つ用いて、エレクトリック的に指向性を狭角にします。
干渉管型の方が複雑な加工を必要とするため、コストがかさんでしまうため、一般製品用として多く用いられるのは二次音圧傾度型です。
超単一指向性マイクの特徴
超単一指向性マイクには、大きく2つの特徴があります。
周りの音がより拾いにくい
超単一指向性マイクは、マイクの周りの音が拾いにくく、より正面の音を捉えやすいという特徴があります。
単一指向性との違いでも解説しましたが、超単一指向性マイクは音を拾う範囲が115°と狭くなっているため、正面以外の音が拾いにくくなっています。
特に、真横からの音に対してはより遮断されやすくなっているため、ノイズが発生しにくいです。
ただし、背面からの音に対しては多少拾うという特徴も持っています。
ハウリングが起きにくい
超単一指向性マイクは、ハウリングが起きにくいという特徴も持っています。
ハウリングは、マイクで拾った音声をスピーカーから流すときに、その音がもう一度マイクで拾われてしまうことで、特定の周波数帯域が増幅して不快な音が発生する現象です。
しかし、超単一指向性マイクは周りの音を拾いにくいという特徴があるため、真横などに設置されているスピーカーの音が入りにくくなっています。
そのため、比較的ハウリングに強く安定して使用することができます。
超単一指向性(スーパーカーディオイド)はどんな使い方に適しているか?
ここからは、超単一指向性(スーパーカーディオイド)マイクがどんな用途に適しているのか、まとめていきます。
ボーカル
超単一指向性マイクは、ボーカルの収音に使われることがあります。
ボーカル収音では、単一指向性マイクの方が使用頻度は高いですが、超単一指向性マイクを使うことでよりピンポイントに収音することができます。
例えば、もう少しボーカルの音量を引き上げたいという場合に、ノイズが増えてしまったり、ハウリングが発生してしまう可能性が出てきます。
超単一指向性マイクを使うことで、気にせずに音量を引き上げて使用することができます。
そうすることで、よりボーカルの些細なニュアンスなどをしっかりと拾うことができます。
テレビ収録(ショットガンマイク)
テレビ収録などでよく使われていることが多いですが、ショットガンマイクは超単一指向性で設計されています。
人の声を一人一人拾いたいけど、近くに他の人がいると被ってしまい綺麗に拾えないことがあります。
そこで、超単一指向性のマイクを使うことで、より範囲を狭めてピンポイントで音声を拾うことができます。
テレビ収録はもちろんですが、ビデオや動画の制作時にも使われているマイクです。
おすすめの超単一指向性(スーパーカーディオイド)マイク
ここまで、超単一指向性(スーパーカーディオイド)マイクの特徴から用途まで解説してきました。
ここからは、超単一指向性マイクを選ぶのにおすすめのマイクをまとめていきます。
SHURE / BETA58A

ライブや宅録など超単一指向性マイクを使用するなら、SHUREのBETA58Aはおすすめのダイナミックマイクです。
SHUREでベストセラーにもなったSM58のマイクのスーパーカーディオイドのタイプになります。
SM58よりも高音域の音抜けが良く、ハウリングもしにくいので使用しやすいマイクです。
声質にもよりますが、ボーカル用としてのマイクをお探しなら一度試してみても良いマイクです。
AKG / P5S

AKGのP5Sも同じくボーカル用として、宅録などで人気のマイクです。
スーパーカーディオイド特性のため、特にリードボーカルに最適です。
デザインもシックな黒で、Webでのストリーミング配信でも映えるマイクです。
価格も5,000円前後と安いため、初めてのスーパーカーディオイドマイクの1本としては使いやすいです。
BOYA / BY-BM6060

テレビ収録や動画製作などで使用できるショットガンマイクが、BOYAのBY-BM6060です。
ハイパスフィルターも搭載しているので、より狙った音をクリアに捉えることができます。
また、S/N比も低く非常にノイズが発生しにくいマイクです。
カメラに直接取り付けることができるショックマウントやウインドスクリーンなど付属品も付いてきます。
まとめ
このページでは、指向性の中でも超単一指向性(スーパーカーディオイド)についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
超単一指向性には、
- 周りの音を拾いにくい
- ハウリングしにくい
という特徴があり、よりピンポイントの音を拾うことができます。
ボーカル収音でも非常に使いやすいので、特に周りの騒音が発生しやすい宅録などでは重宝するのでは無いでしょうか?
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!