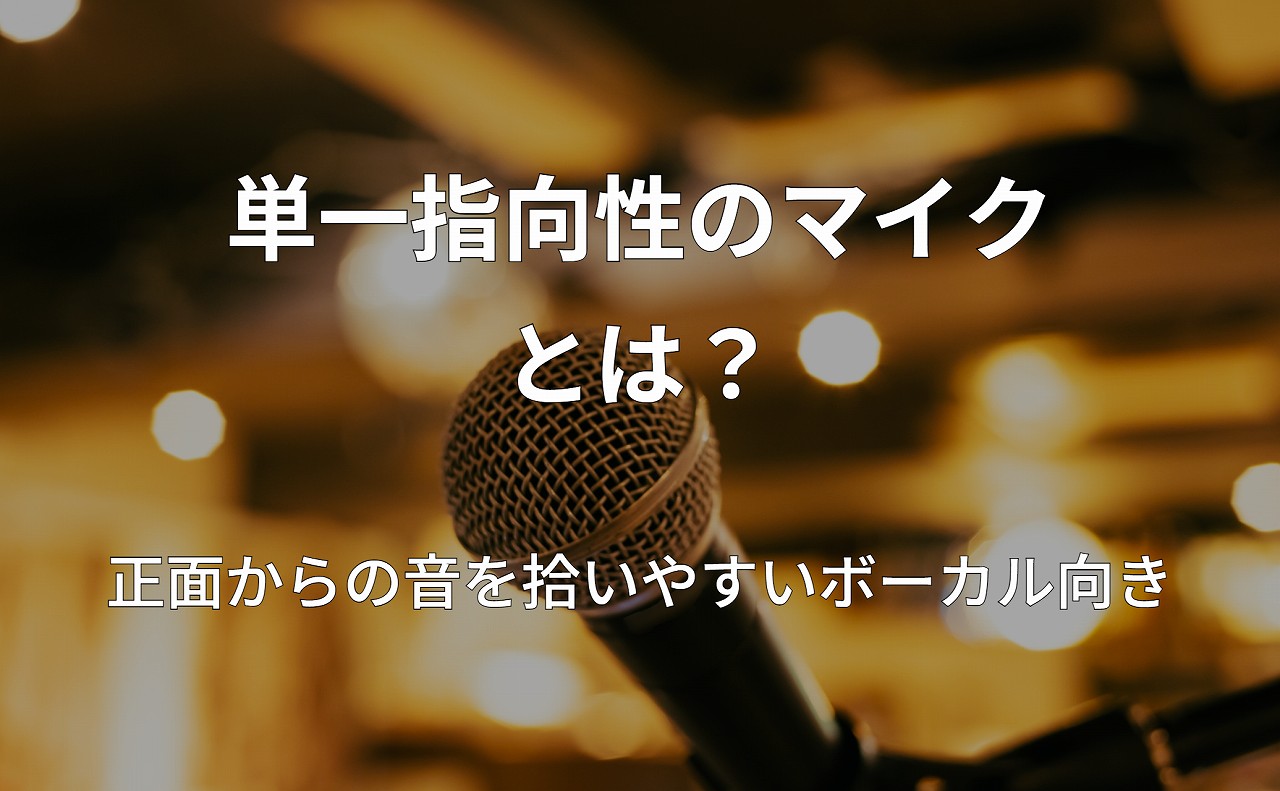マイクは様々な種類やタイプ、性能のものがあり、使い方やどんな音を拾いたいかで、選ぶマイクは異なります。
マイクを選ぶうえで重要になってくる項目の一つが、指向性能という特性です。
指向性能とは、そのマイクがどの方向からの音を拾いやすいか、を示しているものになります。
その中でも、マイクの正面からの音を良く拾うタイプを、単一指向性と呼びます。
このページでは、単一指向性マイクの中でも最もポピュラーなカーディオイドタイプについて、どんなマイクなのか、またどういった使い方に合っているのか、をまとめていきます。
単一指向性(カーディオイド)とはどんなマイク?
まずは、単一指向性マイクがどんなマイクなのか、について解説していきます。
単一指向性には、
- カーディオイド
- サブカーディオイド
- スーパーカーディオイド
- ハイパーカーディオイド
と4種類に分かれていますが、ここでは多くの単一指向性マイクで使われているカーディオイドと呼ばれるタイプについて、記載していきます。
正面からの音への感度が高い指向性能
カーディオイド型は単一指向性の中でも、最もマイクの正面からの音の感度が高く、反対にマイクの背面からの音の感度が低くなっている特徴をもっています。
音の感度の高い、低いというのは、簡単に言えば音を拾いやすいか、拾いにくいかの違いになります。
つまり、単一指向性マイクは、正面からの音を拾いやすく、背面からの音を拾いにくいマイクと言い換えることができます。
また、真横からの音を左右の開く角度として180°とした場合に、カーディオイドタイプは131°までの音を拾えるようにカバーしているので、実は真正面以外からの音もしっかりと拾うことができます。
単一指向性のマイクを使うメリット
正面からの音を良く拾うマイクが単一指向性と解説しましたが、単一指向性マイクを使うメリットは何なのでしょうか?
雑音やノイズが入りにくい
マイクで音を拾う際に、一番注意すべきなのが雑音やノイズを拾わないようにすることですが、単一指向性マイクはこの雑音やノイズが入りにくい、というメリットがあります。
なぜなら、前述したように単一指向性マイクは正面からの音は拾いますが、真横や背面からの音に対しては、拾いにくいように設計されているからです。
もちろん、完全に拾わないというわけではありませんが、大きな音でないとほとんど拾うことはありません。
そのため、単一指向性のマイクが向いている以外の方向からの雑音やノイズが入りにくいです。
ハウリングが起きにくい
単一指向性のマイクは、ハウリングが起きにくいというメリットがあります。
そもそもハウリングの主な原因として、スピーカーからの音をマイクが拾い、その音が再度スピーカーから流れてしまうことで、特定の周波数帯域の音が増幅されて不快な音が発生してしまいます。
ほとんどの場合スピーカーからの音は背面、もしくは横から流されることが多く、マイクの正面からの音を中心に拾う単一指向性マイクだと、このスピーカーの音を拾いにくいです。
そのため、単一指向性マイクはハウリングが起きにくいマイクと言えます。
ただし、スピーカーの音が大きすぎる場合は、単一指向性マイクでも音を拾ってしまう可能性がありますので、その際はスピーカーの音量を下げるか、マイクの入力音声を下げる必要があります。
単一指向性のマイクのデメリット
一方で、単一指向性のマイクにはデメリットも存在します。
入力方向がずれると拾われなくなる
動きながら音を拾う場合に、入力方向が単一指向性マイクの拾う範囲から外れてしまうと、全く拾わないか入力音声が極端に小さくなってしまいます。
当然ではありますが、正面からの音を中心に拾う単一指向性マイクなので、それ以外の角度からの音は拾いにくいです。
そのため、マイクの前にいないで動く場合、例えば演劇などには単一指向性マイクは不向きと言えます。
1本で複数人の音が拾えない
先ほどのデメリットにも似ていますが、単一指向性マイクを使う場合は1人、もしくは多くても2人で、それ以上の人数だと音が拾えない可能性があります。
単一指向性マイクは音を拾う角度が限られているので、その範囲内に収音したい人が集まれないと難しいです。
例えば、漫才だと1本のマイクの前に2人で喋っても音を拾えていますが、人数が増えれば増えるほど音が拾えなくなってしまいます。
低音域が強調される近接効果
単一指向性マイクには、近づいて収音すると低音域が強調されてしまう近接効果、と呼ばれるデメリットがあります。
この近接効果は、マイクの中でもダイナミックマイクにだけ起こることですが、マイクから30cm以内の距離で歌ったり話したりすることで、低音域だけが強調され少しこもったような音で拾われてしまいます。
そのため、ボーカルなどでマイクを使用する場合は、少し離した状態で音を拾うことが多いです。
ただし、近接効果はデメリットだけでなく、この効果を上手に使って演出することも多くあるため、一概にデメリットとは言えません。
また、最近のほとんどの単一指向性マイクでは、近接効果により強調される低音域の入力音圧を下げる調整を行っています。
単一指向性のマイクはどんな使い方に適しているか?
単一指向性のマイクの特徴が分かったところで、ここからは単一指向性のマイクがどんな使い方に適しているのかをまとめていきます。
ボーカル
ボーカルのレコーディングやライブなどに、単一指向性のマイクは使われることが多いです。
なぜなら、単一指向性マイクを使ってボーカルの収音をすることで、ボーカル以外の音を拾わなくすることが出来るからです。
もう少し具体的に言えば、ボーカルの口の前にマイクをセッティングすることが出来れば、ボーカルからの音はしっかりと正面で拾うことができ、それ以外の音は極力拾わないようになります。
そのため、ボーカルの声を収音する際は、ほとんど単一指向性マイクが使われています。
ゲーム実況
パソコンやゲーム機を使ったゲーム実況でも、単一指向性のマイクが使われやすいです。
ゲーム実況では、パソコンの前など固定した位置にいたまま、自分の声を拾うことがほとんどです。
そのため、真正面からの音を拾う単一指向性のマイクを使うことで、自分の声はしっかりと拾って、パソコンからの音は拾わせない、といったことができます。
テレワーク
ゲーム実況と同じく、パソコンを使ったテレワークでも単一指向性のマイクが使われやすいです。
テレワークでもパソコンの前に単一指向性マイクを固定することで、しっかりとマイクの正面から自分の声を拾うことができます。
また部屋の騒音や外からのノイズ音なども拾わずに、相手に声を届けることができます。
おすすめの単一指向性(カーディオイド)タイプのマイク
最後に、単一指向性のカーディオイドタイプでおすすめのマイクを紹介していきます。
SHURE / SM58
ライブ用に世界的に使用されているのが、SHUREから発売されているSM58というマイクです。
ゴッパーという愛称がつけられているこのSM58は、特にライブパフォーマンスで効果を発揮します。
単一指向性かつポップフィルターが内蔵されているため、ボーカルの音をしっかりと捉えて、周りの雑音をカットしてくれるので、よりクリアにボーカルの音声を拾ってくれます。
また、ダイナミックマイクとしても耐久力が高く、多くのバンドやアイドルなどで使われているマイクです。
audio technica / AT4040
ボーカルレコーディングとして使われているのが、audio technicaのAT4040というマイクです。
AT4040はラージダイアフラムタイプのコンデンサーマイクで、ボーカルの音をよりナチュラルにフラットで拾ってくるのが特徴です。
特に、レコーディングでは原音のまま拾ってくることが出来るので、非常にその後の編集がやりやすいです。
marantz Professional / MPM-1000
marantz Professional(マランツプロ)のMPM-1000というマイクも、単一指向性の中で人気の高いマイクです。
MPM-1000のマイクは、パソコンのUSB端子に接続して使用するUSBコンデンサーマイクです。
ゲーム実況やテレワークなどに非常に使い勝手の良いマイクです。
特に、部屋の残響音やノイズを防ぎながら音を拾うことが出来るのでおすすめです。
まとめ
このページでは、マイクの指向性の中でも単一指向性のカーディオイドタイプについてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
単一指向性マイクは、正面からの音に対しての感度が高く、背面からの音に対しての感度が低いのが特徴です。
マイクには、様々な種類がありますが、ボーカルやナレーションなど大きく動かないという場合には、単一指向性マイクが一番使いやすいです。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!